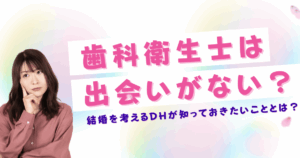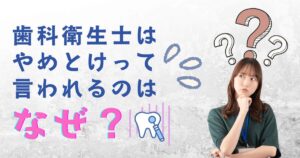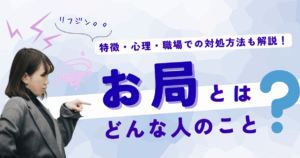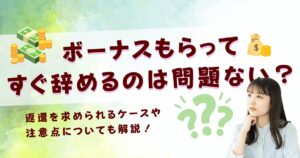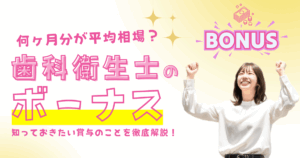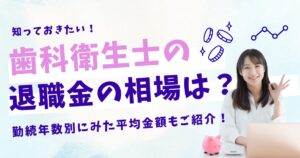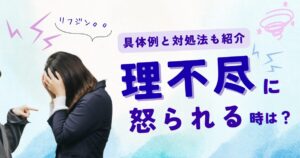ネイルが大好きな人にとって、ネイルOKの職場は理想的ですよね。歯科衛生士の場合、仕事上の様々な理由からNGとされていることが多いのですが、最近はネイルOKの歯科医院も増えつつあります。
どんな歯科医院ならネイルOKなのか、その特徴やルール確認の方法、ネイルOKの求人を探すコツなどについて、詳しくご紹介します!

d latte編集部 ゆうこ
歯科衛生士歴15年のベテラン。矯正歯科専門医院で長年勤務し、小児から成人まで幅広い年代の矯正治療をサポート。患者さんの治療に対する不安を和らげることを得意とし、丁寧なカウンセリングに定評がある。新人歯科衛生士の指導にも力を入れており、後進育成の視点から現場の課題を発信している。
歯科衛生士のネイルは歯科医院によってOKとNGが分かれる!

・ネイルNGの歯科医院の傾向
虫歯や歯周病など、一般的な治療がメインの歯科医院
・ネイルOKな歯科医院の傾向
審美歯科や矯正歯科など、見た目を良くする施術がメインの歯科医院
一般的な治療をメインとする歯科医院は、安全性や衛生面などを最優先に考え、ネイルそのものをNGとしているところが大半です。
一方、審美歯科や矯正歯科などのように、見た目を良くする施術がメインの歯科医院では、控えめなネイルならOKとしている場合があります。
ただ、これはあくまでも大まかな分け方で、最近はネイルOKの職場を望む女性が多いため、歯科医院でもネイルOKのところが増えている傾向にあります。
歯科衛生士のネイルは基本的にNGが多い理由とは?

医療事故を起こすリスク
長い爪で処置をする際、爪が引っかかって患者さんの口腔内を傷つける恐れがあります。また、グローブが気づかないうちに破れてネイルの小さなパーツが外れると、思わぬ事故の原因になる可能性もあります。
ネイルパーツが患者さんの口に入ってしまったり、薬剤に紛れ込んだりすると、医療事故を引き起こす危険があるからです。
手指衛生面・グローブ破損による感染リスク
どんなに丁寧に爪の手入れをしていても、爪先には汚れが溜まりやすいのが難点です。爪先の汚れの中で細菌が繁殖すると、衛生面で大きな問題になります。
また、長い爪はグローブが破損しやすいという危険があります。処置の途中でグローブが破れて爪先が露出すれば、患者さんの口腔内に細菌が付着する恐れがあります。
患者さんにネガティブな印象を与える可能性
派手なネイルをしていると、患者さんが衛生面や安全性で不安を感じる可能性があります。「爪先が汚れていそう」、「長い爪が引っかかりそう」といった余計な心配を与えてしまいかねないからです。
また、身なりが派手であることに、漠然とした不安を感じる患者さんもいます。「チャラチャラしていて施術が下手そう」といった偏見を持つ人もいることを理解しておきましょう。
業務効率が低下しやすい
ネイルをしていると指先の感覚が伝わりにくくなったり、長い爪が邪魔をして細かい作業がしづらくなったりします。
歯のクリーニングや歯石の除去など、歯科衛生士の仕事は指先を使った細かい作業がメインです。しかし、派手なネイルをしていると、それが原因で作業効率が落ちる可能性があります。
医療器具を破損させるリスク
長い爪は患者さんの口腔内を傷つけてしまう恐れがあるだけでなく、大切な医療器具を破損させる心配もあります。
ネイルが引っかかって器具に傷をつけてしまったり、指先の感覚が鈍くなっているせいで床に落としてしまうなど、ネイルが原因で起こりうるトラブルは様々です。また、その結果として安全性や作業効率の低下も招いてしまいます。
職場の秩序が乱れる可能性がある
ネイルに関するルールがあいまいな場合、「派手なネイルはNG」とされていても、どの程度を派手とするかは個人の感覚によって異なります。
すると職場内でも、派手なネイルを好む人やそれを快く思わない人などが出てきて、職場の秩序や調和が乱れてしまいます。そのため、あらかじめネイルをNGとする歯科医院もあるのです。
特にNGなネイルの特徴は?

- 立体的で大きめのパーツ
- スウィングチャームなどの揺れるパーツ
- メタルパーツ
- 大粒ストーンやガラスパーツ
- 派手なカラーやストーン・ラメなどの装飾付きネイル など
剥がれたり外れたりする恐れがあるネイル、汚れが溜まりやすい形状のネイルなどは、安全性や衛生面で問題があります。患者さんの口腔内に誤って落下したり、細菌の付着につながる恐れがあるからです。また、仮にそのようなトラブルの心配がないとしても、患者さんに余計な不安を感じさせてしまうのは避けるべきです。
ネイルOKとしている歯科医院でも、上記に挙げたようなネイルは基本的にNGと考えておいた方がよいでしょう。特にセルフネイルは長持ちしにくかったり、手入れが不十分だったりすることが多いため、注意が必要です。
ネイルOKな歯科医院の傾向

1. 院長の判断で許可している歯科医院
ネイルに関して細かい規定がない歯科医院は、多くの場合に院長の判断でOKかNGかを区別しています。特に若い世代の歯科医師は個性を尊重する傾向にあり、歯科衛生士のファッションに対しても寛容なケースが多いと言えます。
ただし、派手過ぎるネイルは許可されないのが一般的です。これはネイルに限ったことではなく、髪型や髪色などに関しても当てはまることです。

院長先生の考え方によって職場の雰囲気も大きく変わるものですね。個性を大切にしてくれる環境は働きやすさにも繋がりますが、医療現場としての品位も保ちたいという、そのバランス感覚が大切なのでしょう。
2. 爪の保護用のコーティングは認めている歯科医院
トップコートや補強コートなど、爪の保護用のコーティング剤のみをOKとしているところもあります。つまり、透明なネイルであればOKというルールです。
無色透明のコーティング剤は色こそないものの、自然なツヤが生まれて爪がきれいに見えます。ただし、ラメ入りのトップコートなどは目立つため、避けた方がよいでしょう。
3. ベージュや淡いピンクなど華美でないものは認めている歯科医院
控えめな色のネイルならOKという場合は、ベージュや淡いピンクなどが基本になります。本来の爪の色に近いネイルと考えればよいでしょう。
華やかなネイルを好む人には物足りないかもしれませんが、色の選択肢がいくつかあれば、気分によって変えられるというメリットがあります。

清潔感を保ちながらも、ささやかなおしゃれを楽しめるのは嬉しいものです。自然な色合いでも、きちんとお手入れされた指先は患者様に好印象を与えますし、気分転換にもなりそうですね。
4. 審美歯科が中心の歯科医院で美容意識の高い患者様がくる歯科医院
審美歯科は歯の見た目を良くする施術がメインなので、美意識の高い患者さんが多いのが特徴です。そのため、歯科医院やそこで働く歯科衛生士も、洗練されたおしゃれな雰囲気であることが好まれます。
このような歯科医院は、治療がメインの歯科医院と比べると、ネイルOKとしているところが多い傾向にあります。
ネイルOKの歯科衛生士求人の探し方
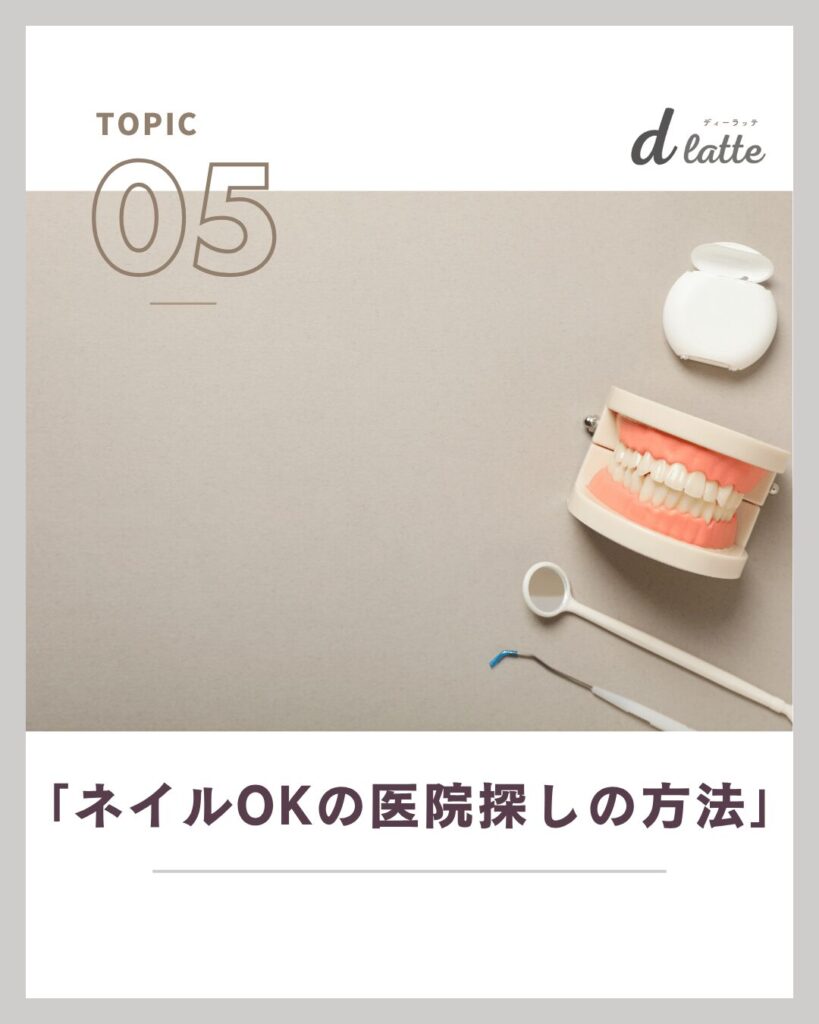
ジョブメドレーの場合
- トップページの職種「歯科」から「歯科衛生士」を選択。
- 都道府県を選択。
- 「市区町村から選択」または「沿線から選択」で希望するエリアを選択し、「検索する」をタップ。
- 希望する「駅・沿線」を選択し、「検索する」をタップ。
- 「特徴から選択」をタップし、「ネイルOK」を選択。
- 希望する「雇用形態・給与」や、ネイル以外に希望する「特徴」があれば選択し、「検索する」をタップ。
ジョブメドレーは医療介護従事者のための求人サイトです。無料の会員登録をすれば、事業所からのスカウトや、希望する条件に合う最新の求人情報をメールやLINEで受け取れます。
ジョブメドレーにも特徴から選択という項目でネイルOKを選択するとそれに合致する歯科医院が出てきます。
グッピーの場合
- トップページ「歯科求人(中途)」から「歯科衛生士」を選択。
- 希望する市区町村を選択。
- 「詳細条件」の「職場環境」から「ネイルOK」を選択。
- その他の希望条件があれば選択または入力し、「検索」をタップ。
グッピーは医療・介護・福祉の転職求人サイトです。無料の会員登録をすれば、直接スカウトを受けたり、採用担当者に匿名で問い合わせやメッセージを送れます。
ジョブメドレー同様、ネイルOKという条件を選ぶとOKとしている歯科医院がでてきます。

ネイルOKとされていても、歯科医院ごとに基準や規定が設けれらていることがほとんどです。どこまでのネイルがOKなのかは確認する必要がありますね。
おすすめの転職サイト!
| 評価項目 | ジョブメドレー | ファーストナビ | デンタルワーカー |
|---|---|---|---|
| 画像 |  |  |  |
| 歯科衛生士求人数 | 18,000件以上 | 24,000件以上 | 7,400件+非公開求人多数 |
| エリア求人数 (例:東京) | 2,500件以上 | 4,700件以上 | 1,100件以上 |
| 掲載情報の充実度 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
| 業界認知度 | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
| 転職エージェント | |||
| サイトの使いやすさ | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| 口コミ | ジョブメドレーの口コミはこちら | ファーストナビの口コミはこちら | デンタルワーカーの口コミはこちら |
| 詳細 | くわしく | くわしく | くわしく |
入社後にネイルOKかどうかを確認する方法
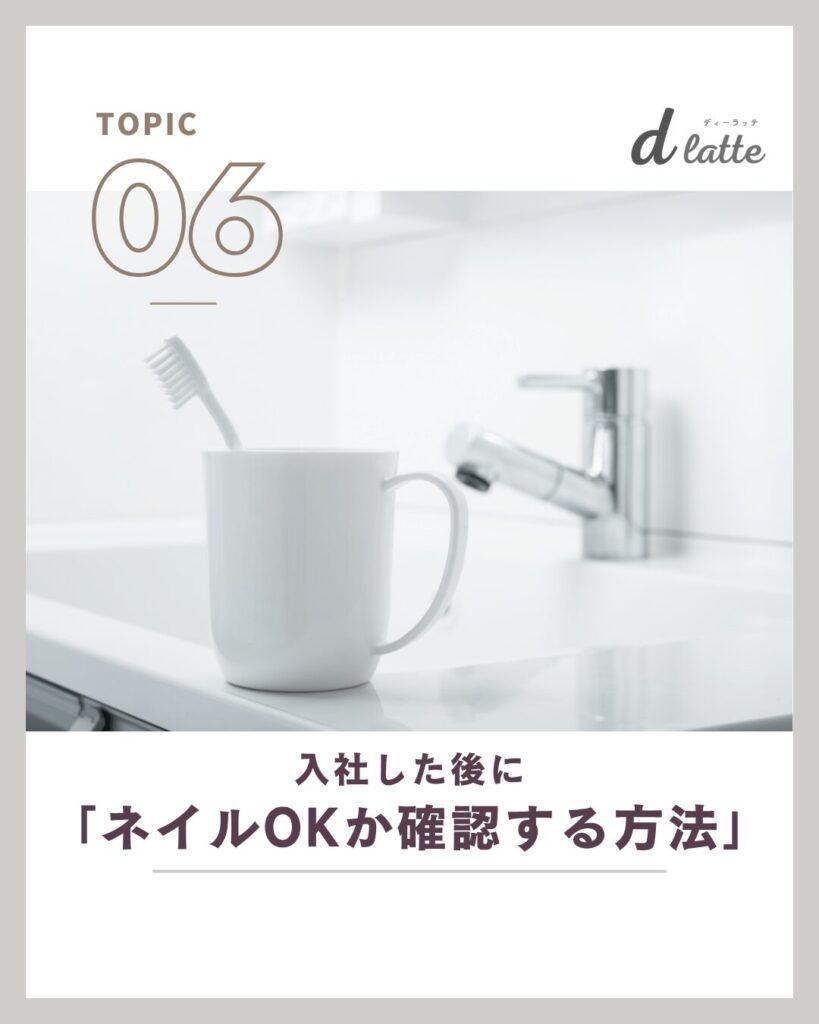
先輩スタッフに確認する
職場でのネイルがOKかどうか知りたい時は、先輩の歯科衛生士さんに確認するのが確実です。ネイルOKの場合でも、許可されている色などに決まりがあることが多いため、具体的に教えてもらいましょう。
また、先輩のネイルを参考にすれば、爪の長さやネイルの色などで院長から注意される心配もなくなります。

職場の暗黙のルールは先輩スタッフが一番よくわかっていルはず。実際の事例を見せてもらえれば、どの程度まで大丈夫なのか具体的にイメージできて安心です。
就業規則をチェックする
就業規則がある場合は、ネイルに関する記載がないか確認してみましょう。身だしなみに関する規則は「服務規律」という項目に記載されています。
ネイルOKとされていても、服務規律で爪の長さやネイルの色、パーツの使用禁止などが決められている場合があります。服務規律は従業員が守らなければならないルールなので、違反しないよう気をつけましょう。
直接院長に聞く
ネイルに関する具体的なルールがなく、先輩の歯科衛生士さんに聞いても分からない時は、院長に直接確認することが肝心です。
例えば、在籍する歯科衛生士が少人数で、誰もネイルをしていない場合、院長がルールを設ける必要性を感じていない可能性もあります。勝手な独断でネイルをすると、職場の雰囲気が悪くなることもあるので注意しましょう。
ネイルが原因で患者様からクレームになるケースも知っておこう!
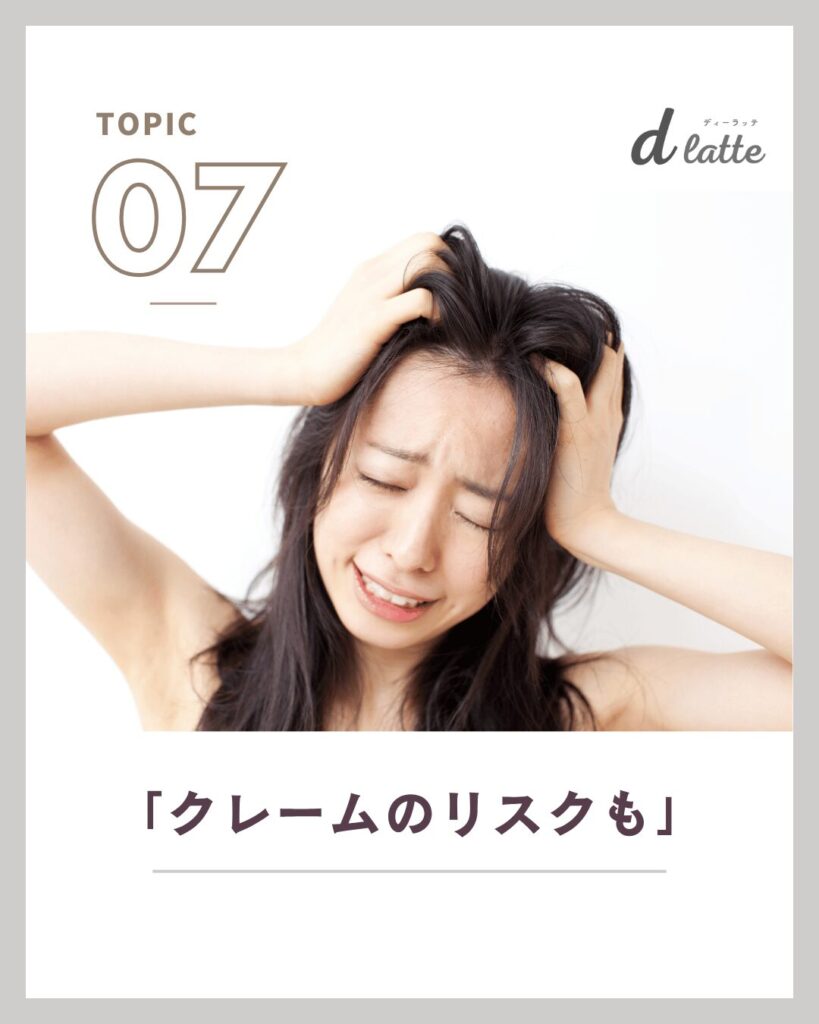
患者さんの中には、ネイルをしている歯科衛生士に処置されることに抵抗を感じる人もいます。特に長い爪や派手なネイルは衛生面で不安視されやすく、実際にクレームになるケースもあります。
また、ネットの口コミやSNSなどに投稿されれば、歯科医院そのものに対する信頼性も低くなってしまうことを理解しておきましょう。
まとめ
ネイルOKの歯科医院は増えている傾向にありますが、業務上の問題から派手なネイルはNGとされているのが一般的です。ネイルOKの歯科医院に転職したい方は、「ネイルOK」と記載されている求人先を選びましょう。また、どのようなネイルならOKなのかをきちんと確認することも大切です。
しっかりルールを守ってネイルを楽しんでくださいね!