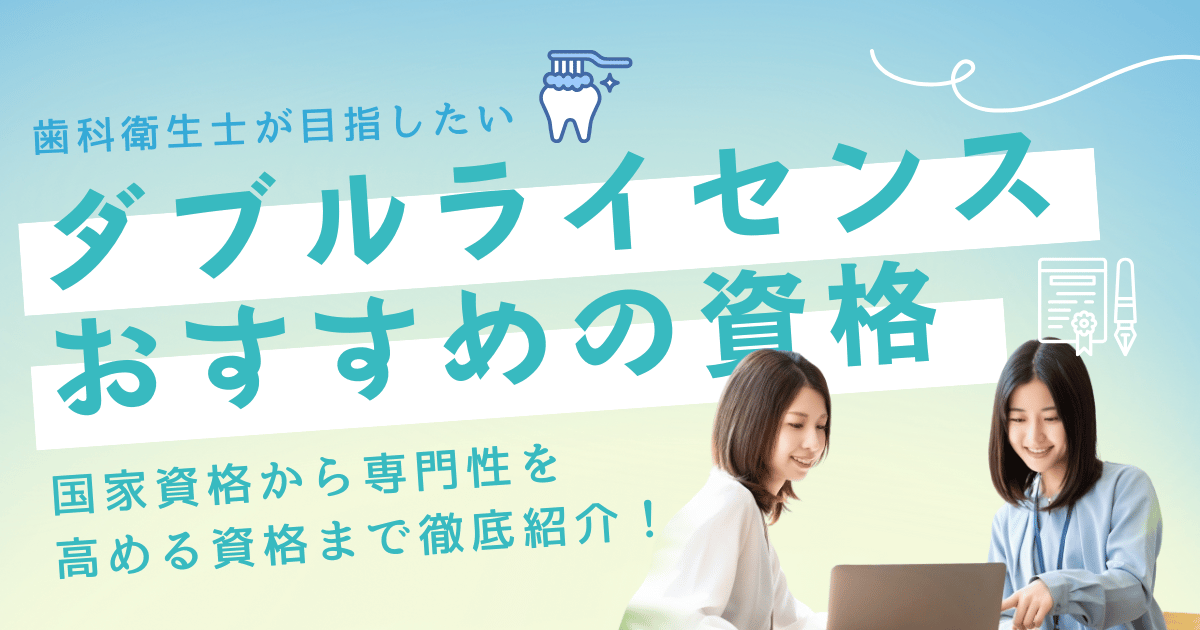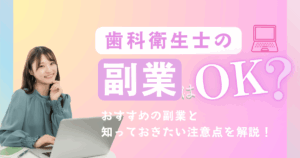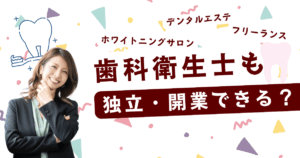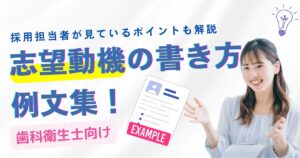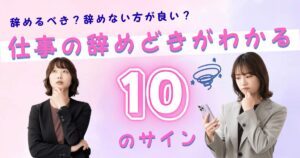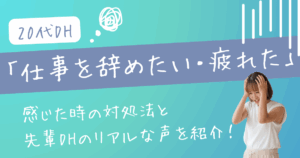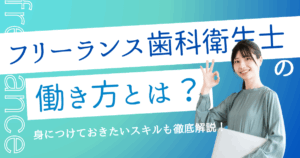2つの資格を取得する「ダブルライセンス」は、キャリアアップに有効な手法の一つ。すでに国家資格を有する歯科衛生士なら、ダブルライセンスにチャレンジしやすいというメリットがあります。
歯科衛生士のダブルライセンスにおすすめの資格は、国家資格からビジネス系の資格まで種類が豊富!仕事の幅が広がって、転職にも役に立ちますよ。

d latte編集部 ちはる
歯科衛生士歴7年。小児歯科専門医院で子どもたちの口腔健康管理に従事。歯科恐怖症の子どもたちとも信頼関係を築くのが得意で、保護者からの信頼も厚い。子どもの成長に合わせた口腔ケア指導や、家族ぐるみでの予防意識向上に取り組む。明るく親しみやすい人柄で、子育て世代に寄り添う記事を執筆している。
歯科衛生士のダブルライセンスとは?
| 医療・福祉系の国家資格 | 難易度が高い分取得できるとアドバンテージ大 |
| 歯科衛生士の専門性を高める資格 | 歯科衛生士としての信頼感・価値を高められる |
| ビジネススキルを高める資格 | 汎用性が高くポータブルスキルとなって活かせる |
歯科衛生士のダブルライセンスにおすすめの資格は、主に上記の3つのジャンルに分かれます。国家資格は合格までに時間も費用もかかりますが、活躍の場が大きく広がるチャンスに恵まれます。一方、専門性を高める資格は臨床業務のスキルアップになることが多く、ビジネス系の資格は歯科医院の運営や接客などに役立ちます。
資格の種類によって活かし方も大きく異なるため、まずは自分がどのようにキャリアアップしたいのかを明確にすることが大切です。また、仕事をしながら勉強するための時間配分や、費用の算出方法なども考えてみましょう。

目指す方向性によって選ぶべき資格も変わってくるので、まずは将来のビジョンを描くことが大切ですね。それぞれのジャンルで得られるスキルも違うので、慎重に選びたいところです。
歯科衛生士におすすめの医療系の国家資格8選!
国家資格を取得するには、大学・短大・専門学校のいずれかに通う必要があるのが一般的です。時間も費用もかかり、合格率が低い難関の資格もありますが、取得すれば仕事の選択肢がかなり広がります。また、資格によっては独立も可能です。
1. 歯科技工士
歯科技工士は歯の詰め物や被せ物・入れ歯・矯正装置などを作成する技術職です。歯科衛生士とのダブルライセンスにより、精度の高い技工物を作れるようになったり、患者さんに技工物のメンテナンスを指導できるといったメリットがあります。
歯科技工士の主な職場は、歯科技工所・歯科医院・歯科がある病院などです。また、独立して歯科技工所を開業することも可能です。国家試験の受験資格を得るには、専門学校・大学・短大などで2年以上学ぶ必要があります。一部の学校には夜間部も併設されています。

患者様により質の高いケアを提供できるようになる、とても専門性の高い組み合わせですね。技工物の作製からメンテナンス指導まで一貫して携われるのは大きな強みになりそうです。
2. 歯科医師
歯科医師は歯の治療・抜歯・外科手術などの医療行為を行う職業です。歯科衛生士と歯科医師の両方の資格を持つ人はかなり限られますが、実際に院長として歯科医院を開業している人もいます。ダブルライセンスなら、患者さんの口腔メンテナンスから治療までを全て担えるというメリットがあります。
国家試験を受けるには、歯科大学や大学の歯学部で6年間学ぶ必要があります。さらに、合格後は指定の病院や歯科医院で1年以上の臨床研修を行うことも義務付けられています。

予防から治療まで全てを担えるのは、患者様にとって最高の安心感を提供できますね。長い道のりですが、歯科衛生士の経験があるからこそ得られる深い理解もありそうです。
3. 管理栄養士
管理栄養士はその人の体調や体質などに合わせて、最適な栄養指導や栄養管理を行う人です。歯科における管理栄養士の役割には、口腔機能が低下している高齢の患者さんの栄養指導や、歯周病と深い関わりがある糖尿病の患者さんの食事指導などがあります。
管理栄養士は大学・短大・専門学校において所定の単位を取得し、国家試験に合格することで資格を得られます。ちなみに、混同されがちな「栄養士」は国家資格ではなく、主に健康な人を対象とした栄養指導を行います。

口腔と全身の健康をつなぐ視点で患者様をサポートできるのは素晴らしいですね。特に高齢の方や生活習慣病をお持ちの方には、とても心強い存在になれるでしょう。
4. 看護師
看護師には患者の身体ケア・医師の診療の補助・健診の採血や補助など、様々な仕事があります。患者さんの口腔環境は病状に大きく影響することが多いため、看護師と歯科衛生士の連携は非常に重要です。ダブルライセンスがあれば、口腔ケアと医療ケアの両方を受け持つことができます。
看護師の資格には正看護師と准看護師があり、国家資格にあたるのは正看護師です。正看護師の国家試験を受けるには、大学・短大・専門学校で3,000時間以上の看護過程を修了する必要があります。

医療現場での口腔ケアと全身ケアの連携は本当に重要ですね。両方の視点を持っていることで、患者様にとってより包括的なケアを提供できそうです。
5. 保育士
保育士は乳幼児の保育や、保護者への保育指導などを行う職業です。大学・短大・専門学校・通信教育などで所定の単位を取得するか、一定の年数以上の実務経験があれば、国家試験の受験資格を得られます。
歯科衛生士と保育士のダブルライセンスは、小児歯科の子供の患者さんのケアや、子供連れの患者さんのための一時預かりなど、様々な場面で役立ちます。常勤の保育士を必要とする小児歯科などでは、ダブルライセンスの保有者が優遇されるはずです。

子どもとの接し方を専門的に学んでいることで、小児歯科では本当に重宝されるはず。お子様連れの患者様にも安心してもらえる、とても温かいサポートができそうです。
6. 言語聴覚士
言語聴覚士は、食事や会話に不便を感じている患者さんにリハビリを指導する職業です。国家試験の受験資格を得るには、指定の大学・短大・専門学校のいずれかを卒業する必要があります。
歯科医院では高齢者の嚥下機能の訓練や、子供の口腔機能の発達サポートなどを行います。また、訪問歯科や介護施設などでも、言語聴覚士の活躍が期待されます。言語聴覚士の仕事は歯科衛生士の口腔ケアと連携して行うことが多いため、ダブルライセンスが非常に役に立ちます。

口腔機能と摂食・嚥下機能は密接につながっているので、両方の専門知識を持てるのは大きな強みですね。特に高齢者ケアの現場では、本当に必要とされる人材になれますね。
7. 社会福祉士
社会福祉士は様々な悩みや問題を抱える人たちの相談に乗り、最適なサポートを受けられるように支援する職業です。歯科に関するものでは、通院が困難な高齢者に訪問歯科を紹介したり、経済的あるいは精神的な理由などで歯の治療ができない人に、適切な支援を行う施設や機関を紹介するといった事例があります。
受験資格を得る条件は、卒業した大学・短大が一般か福祉系かによって異なり、養成施設で1年以上学んでいることや、相談援助の実務経験があることなどが必要になります。

患者様の抱える様々な問題を包括的に支援できるのは、とても意義深いお仕事ですね。歯科治療の必要性だけでなく、その背景にある課題まで理解して寄り添えるのは素晴らしいです。
8. 介護福祉士
介護福祉士は介護が必要な人の身体ケアや、生活のサポートなどを行う職業です。歯磨きができない人の口腔ケアも業務の一つですが、歯科衛生士とのダブルライセンスなら、虫歯・歯周病の早期発見や歯石の除去など、より的確なケアが可能になります。
国家試験を受けるにはいくつかのルートがありますが、最も多いのは3年以上の実務経験を積み、研修を受ける方法です。介護士としてのスキルを磨きながら受験に備えられるため、社会人でも取得しやすい国家資格だと言えます。

実務経験を積みながら資格取得を目指せるのは、働く人にとって取り組みやすい制度ですね。介護現場での口腔ケアの質向上にも大きく貢献できるはず。
歯科衛生士の専門性を高める関連資格5選!
得意な分野がある人や、より専門的なスキルを身につけたいという人には、その道のスペシャリストになるための資格がおすすめです。歯科衛生士の実務経験があれば受験できる資格が多いため、働きながら取得を目指せるというメリットもあります。
1. 認定歯科衛生士
認定歯科衛生士とは、特定の分野において高い知識や技術を有すると認められた歯科衛生士のことです。認定分野は以下の3つに分かれます。
【認定分野A】
- 生活習慣病予防
- 摂食嚥下リハビリテーション
- 在宅療養指導・口腔機能管理
- 糖尿病予防指導
- 医科歯科連携・口腔機能管理
- 歯科医療安全管理
【認定分野B】
- 障害者歯科
- 老年歯科
- 地域歯科保健
- 口腔保健管理
- う蝕予防管理
【認定分野C】
- 研修指導者・臨床実地指導者
取得の方法はそれぞれ異なり、指定の研修を修了したり、特定の団体等の推薦を受けるなどの手続きが必要です。

自分の興味や得意分野に合わせて専門性を深められるのは魅力的ですね。患者様により質の高いケアを提供できるとともに、キャリアの方向性も明確になります。
2. インプラント専門歯科衛生士
インプラント専門歯科衛生士は、日本口腔インプラント学会が認定する資格です。インプラント治療のスペシャリストとして、オペのアシストや術前・術後のケアなどを担当するのが主な業務です。
認定を受けるには、日本口腔インプラント学会の会員であることや、インプラント治療の介助などの実務経験があること、専門医の推薦があることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。また、認定期間は5年間とされており、定期的に指定の単位を取得することも必要です。
3. ホワイトニングコーディネーター
ホワイトニングコーディネーターは、日本歯科審美学会が認定する資格です。歯科衛生士だけを対象としており、ホワイトニングの正しい知識や技術を持つ人に与えられます。ホワイトニングは審美歯科の中でも人気の高い施術なので、資格があることで患者さんからの信頼性が増すというメリットがあります。
認定の条件は講習会の受講や受験、学会の会員であることなどです。認定期間は3年間で、更新にはセミナーや講習会などへの参加が必要です。更新を機会に新しい知識を得たり、人脈を広げたりするチャンスにもなります。

人気の高いホワイトニングで専門性をアピールできるのは素晴らしいですね。定期的な更新で常に最新の知識を学べるのも、患者様により良いサービスを提供する上で大切です。
4. トリートメントコーディネーター
トリートメントコーディネーターは、患者さんに治療について丁寧に説明したり、不安や疑問などについてヒアリングしたりする存在です。歯科医師と患者さんの間に立つことで、双方のコミュニケーションを円滑にする役割があります。
資格の認定は日本歯科TC協会やTCマスターカレッジが行っており、どちらも段階を踏んでステップアップできる制度になっています。上級クラスでは後輩の育成や、歯科医院の経営などについての知識も得られます。

歯科医師と患者様の架け橋となる、とても重要な役割ですね。コミュニケーション能力を活かしながら、双方にとって安心できる環境作りに貢献できそうです。
5. 介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護を必要とする人が介護保険を利用してサービスを受けられるよう、ケアプランを作成したり、事業者と結びつけたりする職業です。歯科衛生士として5年以上の実務経験がある人は、受験資格の条件を満たします。
ダブルライセンスがあれば、訪問歯科が必要と判断した人などに対し、自身でケアプランを作成したり、担当のケアマネジャーと対等な立場で話し合いができたりします。
歯科衛生士のビジネススキルを高める関連資格!
ビジネススキルを高める資格は、歯科医院の経営や人材育成、スタッフ同士のコミュニケーション力のアップ、患者さんへの接客スキルの向上などに役立ちます。また、歯科業界とは異なる業種に転職したい時にも、資格保有者であることが有利に働きます。
1. 医療事務資格
医療事務の仕事は、医療機関の受付や会計、レセプト(診療報酬明細書)の作成、カルテの整理など、多岐にわたります。実は資格がなくてもできる仕事なのですが、医療保険制度に則った会計業務などは、専門的な知識が必要とされるため、資格がある方がスムーズに行えます。
医療事務の資格は様々な団体によって制定されている民間資格で、種類が豊富です。また、市販のテキストや通信講座で学べるため、仕事をしながらチャレンジしやすい点も魅力です。
2. 接遇マナーインストラクター
接遇マナーとは、顧客に満足してもらえるような接客・サービスを提供するために必要なマナーのことを指します。そして、その接遇マナーを指導する立場にあるのが「接遇マナーインストラクター」です。歯科医院においても、接遇マナーは患者さんから良い評価を得るために必要なスキルの一つです。
接遇マナーインストラクターの養成は、日本接遇教育協会やICBI(養成スクール)などの養成講座で行っています。講座を修了すると認定証が発行され、フリーランスの講師として活動できるようになります。

患者様に安心感と信頼感を与える接遇スキルは、医療現場では本当に重要ですね。講師として他のスタッフに指導できるようになれば、医院全体のサービス向上にも貢献できそうです。
3. NLP
NLP(Neuro- Linguistic-Programming)は日本語で「神経言語プログラミング」と呼ばれる心理学です。自分の中でパターン化された思考や行動を紐解き、自己実現力やコミュニケーション力を向上させることを目的とした学問です。
NLPは歯科医院においても、患者さんのカウンセリングやスタッフ同士の意思疎通のために用いられています。NLPの資格認定は様々なスクールで行っており、講座を受講することで得られる資格がほとんどです。

患者様の心理を理解して適切にコミュニケーションを取れるスキルは、歯科衛生士にとって本当に価値がありますね。スタッフ間の連携向上にも活かせるのは魅力的です。
4. MOS
MOSは「マイクロソフト オフィス スペシャリスト」のことで、Excel・Word・PowerPointなどの操作スキルを評価する認定制度です。歯科業界でも資料作成やデータ管理など、様々な業務で必要とされるスキルなので、資格を取得していれば、どの職場でも即戦力として仕事ができます。
MOSの試験は誰でも受験可能で、全国約1,500もの試験会場から最寄りの場所を選んで受験できます。また、オフィス製品のバージョンごとに試験が用意されているため、使い慣れたバージョンの試験を選べます。
5. ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーは、お金に関する相談に乗ったり、目標を叶えるために必要な資金計画を一緒に立てたりする職業です。歯科医院専門のファイナンシャルプランナーもおり、開業プランの作成・経営上の課題の解決・院長の資産形成などに関するアドバイスを得意としています。
ファイナンシャルプランナーの資格には、国家資格の「FP技能士」と民間資格の「AFP」「CFP」があります。FP技能士は3段階に分かれており、誰でも受験できるのは「3級FP技能士」です。その他の資格には受験に必要な条件があるため、順番にステップアップすることがおすすめです。
歯科衛生士がダブルライセンスを取得するメリットとは?
- キャリアの幅が広がる
- 職場での価値・信頼性が高まる
- 将来の独立・副業・転職にも強くなる
1. キャリアの幅が広がる
歯科衛生士の多くは、歯科医院において一般的な臨床業務を担当しています。しかし、他の資格も取得すれば、より専門的な業務に携わったり、臨床業務以外の仕事も担えたりできるようになります。
資格を持たなければできない仕事もあるため、ダブルライセンスはキャリアの幅を一気に広げる力を持っていると言えます。
2. 職場での価値・信頼性が高まる
資格があるということは、その分野に精通しているという証になります。そのため、職場でも「この仕事は○○さんに任せよう」、「分からないことは○○さんに聞けば安心」といったように、有資格者が頼りにされる立場になります。また、資格によっては院長からアドバイスを求められたり、後輩の教育係に任命されたりする可能性もあります。

専門性を認められて頼りにしてもらえるのは、仕事のやりがいにも大きく繋がりますね。後輩指導を通じて自分自身も成長できるという、良い循環も生まれそうです。
3. 将来の独立・副業・転職にも強くなる
資格の取得は今の職場だけでなく、将来の働き方にも大きく関わります。副業が可能な職場であれば、資格を活かしてフリーランスとして働き、独立に備えることも可能です。また、転職の際にも、資格があることは大きな武器になります。同じ歯科業界に転職するのはもちろん、医療・介護・事務など、資格によって職種の選択肢が増えるという利点があります。
歯科衛生士がダブルライセンスを取得するデメリットとは?
- 時間的・金銭的コストがかかる
- 実務に活かせるとは限らない
1. 時間的・金銭的コストがかかる
資格の受験に必要な条件は様々で、決められた単位の取得や、指定の講座の受講などが義務付けられているケースがほとんどです。
特に国家資格は大学・短大・専門学校に通わなければ受験資格を得られないことが多いため、歯科衛生士の資格を取得した時と同程度か、それ以上の時間と費用がかかると考えておいた方がよいでしょう。

国家資格となると、かなりの覚悟と準備が必要になってきますね。長期的な計画を立てて、家庭や仕事との両立も慎重に検討する必要がありそうです。
2. 実務に活かせるとは限らない
実は資格を取得した人の中には、「仕事でなかなか活かせない」という悩みを持つ人も少なくありません。その原因は「今の職場では必要がないスキルだった」、「実務経験がないと強みにならない」、「具体的な目的がなく、なんとなく取った資格だから」など様々です。
資格を無駄なく活かしたいのであれば、取得後の仕事のビジョンを明確に持つことが大切だと言えます。
まとめ
歯科衛生士はすでに国家資格の保有者なので、無資格の人よりもダブルライセンスを取りやすいのがメリットです。今の職場でできることを増やしたい人や、転職あるいは独立を考えている人などは、ダブルライセンスがキャリアを広げる有効な手段になります。理想の働き方を思い描いたら、そのために必要な資格を取得してみてはいかがでしょうか?