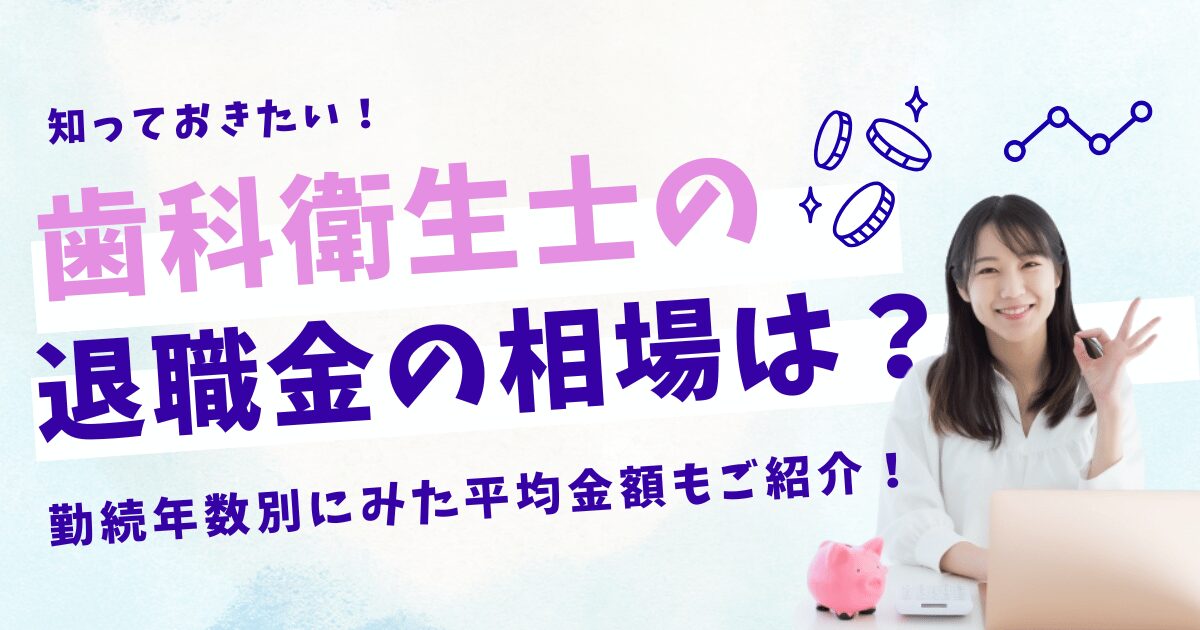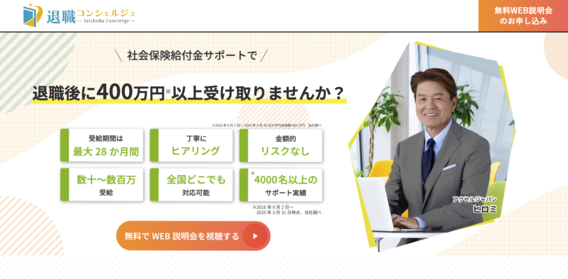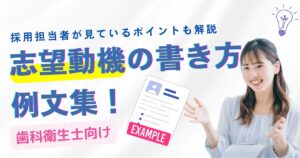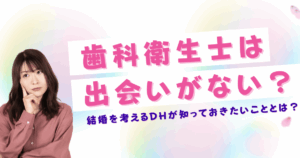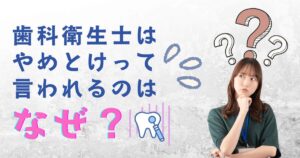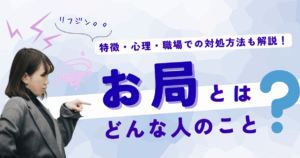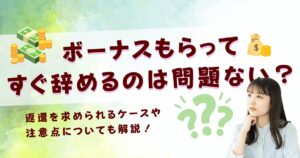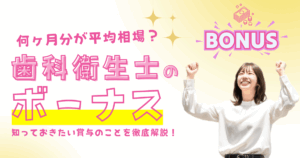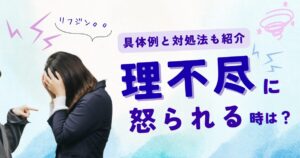勤務先を退職したいと思った時や、定年退職が近づいてきた時、「退職金」について知りたいと思う人はきっと多いはず。歯科衛生士の退職金はいくらくらいなのか、そもそも自分は受け取れるのかなど、分からないことも多いですよね。
退職金が支払われる場合、その金額は勤続年数や月収などによって異なります。
この記事では、歯科衛生士の退職金の相場や大まかな計算方法、税金の問題などについて解説します!

d latte編集部 かおり
歯科衛生士歴9年。インプラント治療を専門とするクリニックで、術前術後のメンテナンスを担当。患者さんの長期的な口腔健康維持をサポートしている。セミナーや勉強会への参加も積極的で、常に新しい知識と技術の習得に努めている。同僚との情報共有を大切にし、チーム医療の向上に貢献している。
※本記事で紹介している商品にはPR商品を含みますがランキング・コンテンツ内容はd latte編集部調査をもとに作成しています。また本記事内の情報は一般的な知識であり、自己判断を促すものではありません。
歯科衛生士の退職金の相場!

| 【医療・福祉系】学歴別の退職金の相場 | |
|---|---|
| 高校卒 | 332万3千円 |
| 高専・短大卒 | 312万1千円 |
| 大学卒 | 342万4千円 |
上記の表は、東京都産業労働局の「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年)」を参考にしています。歯科衛生士に限定したデータはありませんが、医療・福祉系の職業で定年退職した場合の退職金の相場は、約312万~342万円となっています。
ただし、これは東京都内にある従業員10~299人の中小企業を対象とした調査です。そのため、住んでいる地域や従業員の人数などによって、退職金の相場もそれぞれ異なると言えます。また、退職金は勤続年数・役職・退職事由(自己都合退職か会社都合退職か)などによっても異なります。

退職金の相場を知ると、長く働く価値を改めて実感しますよね。地域や医院の規模で差があるとはいえ、専門職としてのキャリアを積み重ねることの意味を考えるきっかけになるのではないでしょうか。
退職金は必ずもらえる?

支払い義務はなく、勤務先の方針で決まる!
退職金は勤務先が「退職金制度」を設けることで支払い義務が発生します。しかし、退職金制度自体に導入の義務はなく、勤務先が退職金制度を設けていなければ、退職金を支払う義務も受け取る権利もありません。
勤務先に退職金制度がある場合は、就業規則に詳細が記載されています。また、求人票にも「退職金制度あり」と記載されているため、面接を受ける前に確認することが可能です。
一方、正式な退職金制度はないものの、小規模の歯科医院の中には、院長の裁量で少額の退職金が支給されるところもあります。このような場合は就業規則に記載されていないことが多く、退職金が必ず支給されるという確約もないのが現状です。
【雇用形態別】歯科衛生士の「退職金あり・なし」の割合
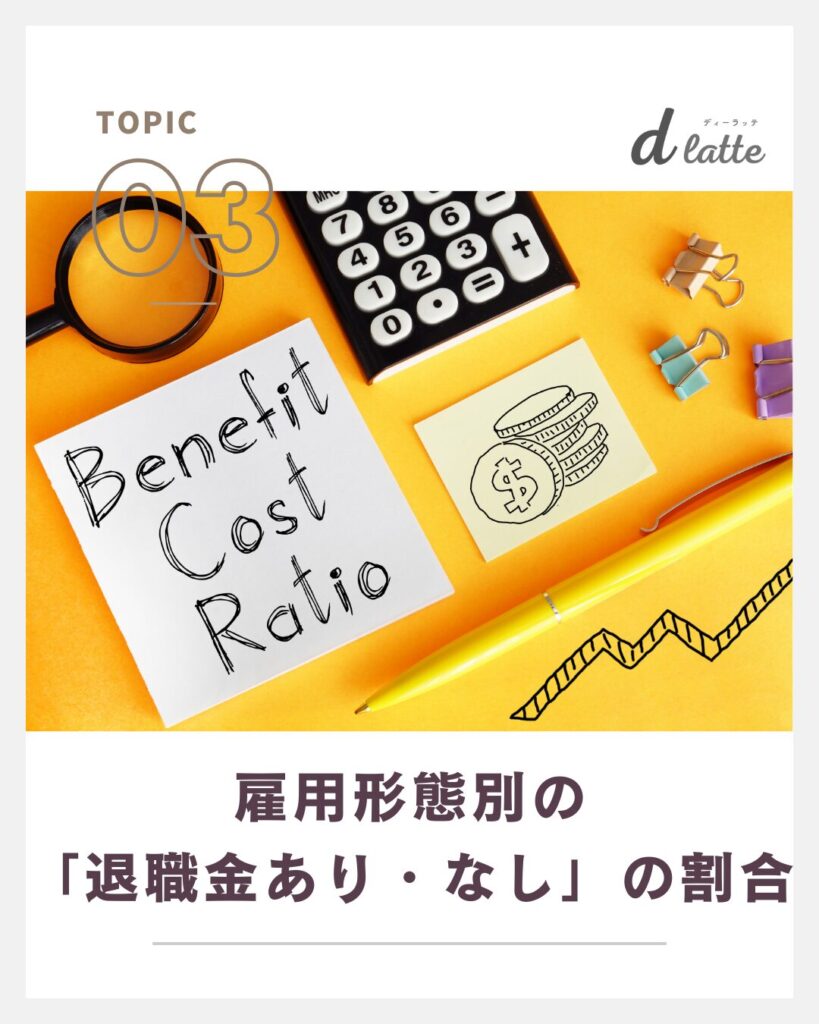
| 就業形態 | 退職金あり | 退職金なし |
|---|---|---|
| 常勤 | 76.8% | 14.1% |
| 非常勤 | 8.5% | 78.8% |
日本歯科衛生士会の「歯科衛生士の勤務実態調査報告書(令和7年)」によると、「退職金制度がある」と答えた歯科衛生士は、常勤が76.8%、非常勤が8.5%という結果になりました。
一方、「退職金制度がない」と答えたのは非常勤の人が圧倒的に多く、常勤の人でも14.1%を占めています。
ちなみに、「退職金制度があるか分からない」と答えた人は、常勤が9.1%、非常勤が12.7%でした。この結果から、退職金制度の有無を知らないまま勤務している人も一定数いることが分かります。
【勤務先の種類別】の退職金事情!歯科診療所では約6割が制度あり
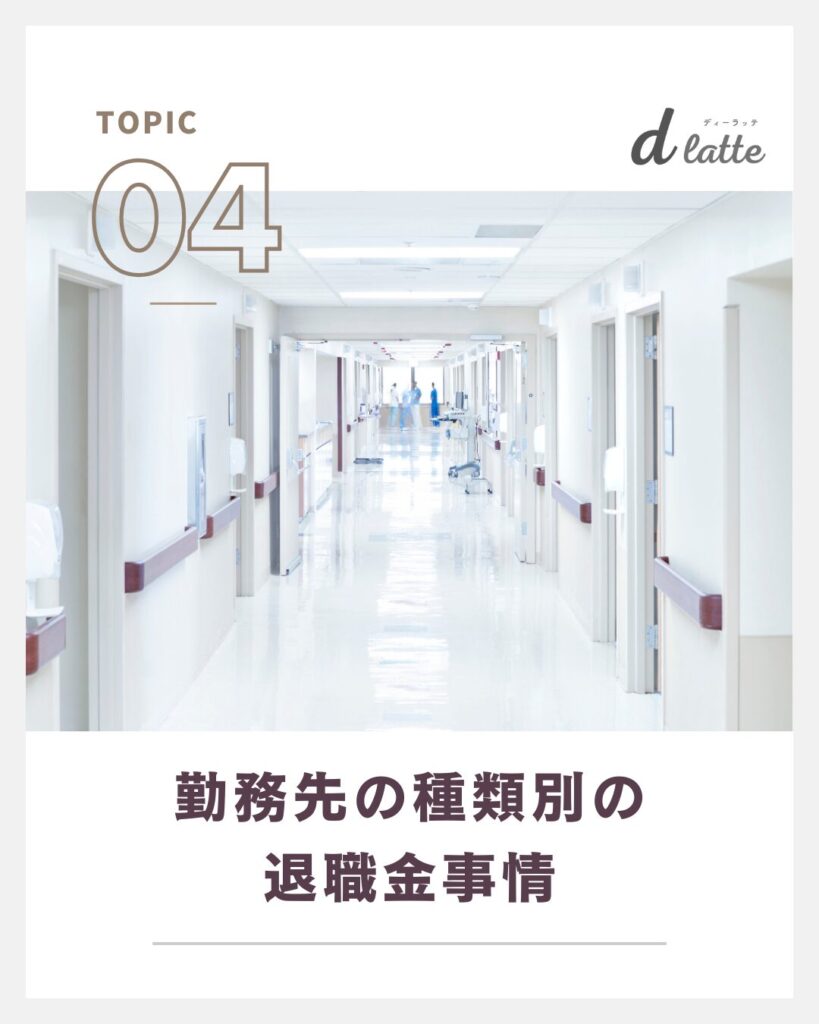
| 勤務先の種類 | 退職金ありの割合 |
|---|---|
| 歯科診療所 | 61.6% |
| 病院・大学病院 | 90.5% |
| 歯科衛生士教育養成機関 | 89.5% |
| 行政 | 74.7% |
| 介護保険施設等 | 86.4% |
上記の表は、日本歯科衛生士会の「歯科衛生士の勤務実態調査報告書(令和7年)」を参考に作成した、勤務先別の「退職金制度がある」と答えた歯科衛生士の割合です。
診療所に勤務する歯科衛生士で「退職金がある」と答えた人は61.6%となっており、他の勤務先よりも低い割合であることが分かります。
大半の歯科医院は個人経営なので、病院などの大規模な勤務先と比べると、退職金制度を導入していないケースが多いのだと言えるでしょう。

診療所で働く仲間の約4割が退職金制度なしという現実は、想像以上に厳しいものですね。個人経営ならではの事情もあるでしょうが、長期的なキャリア設計を考える際に、福利厚生の確認がいかに大切かを物語っています。
退職金はどうやって計算する?
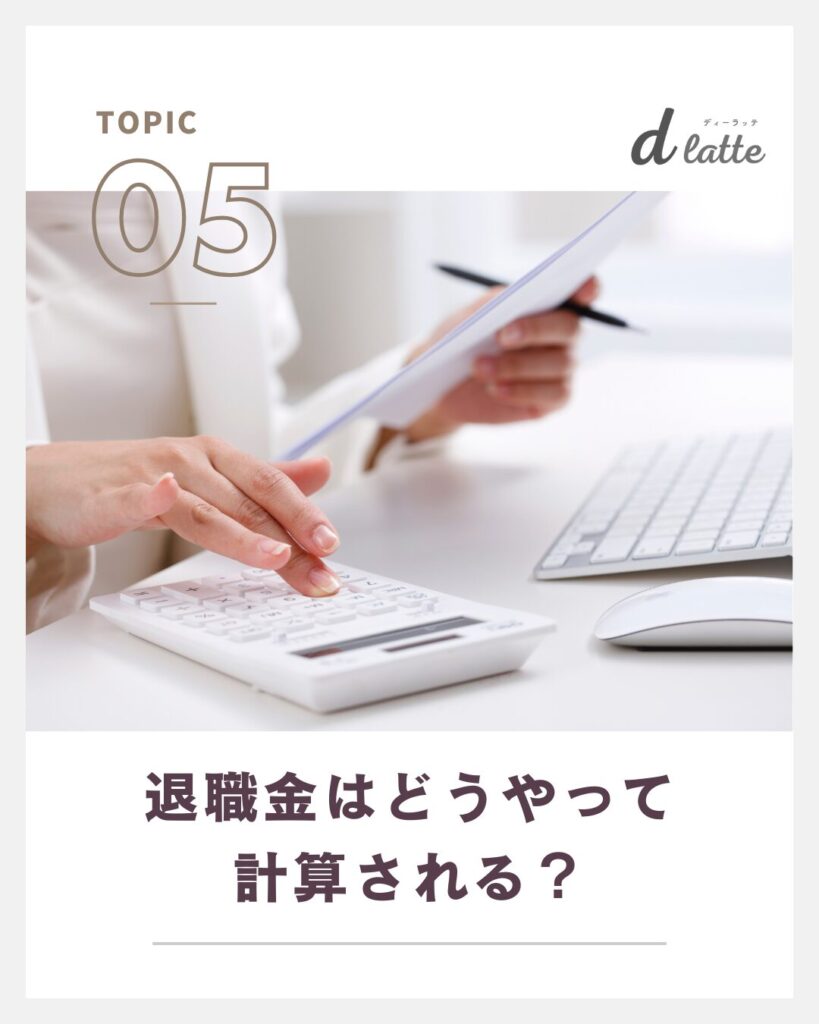
- 月収の1~4ヶ月分が一般的
- 勤続年数に応じた支給率をかける
- 役職などに応じて加算
- 自己都合退職などの場合は既定の割合を減算
退職金の計算方法は勤務先によって異なりますが、月収の1~4ヶ月分に相当する金額になるのが一般的とされています。
また、役職に応じてさらに金額が加算されたり、自己都合退職や勤務態度が悪いなどの場合は減算されたりするのが一般的です。いずれも勤務先が規定する金額や割合が用いられるため、勤務先の退職金制度をよく理解した上で計算する必要があります。
【勤続年数別】歯科衛生士の退職金の平均金額
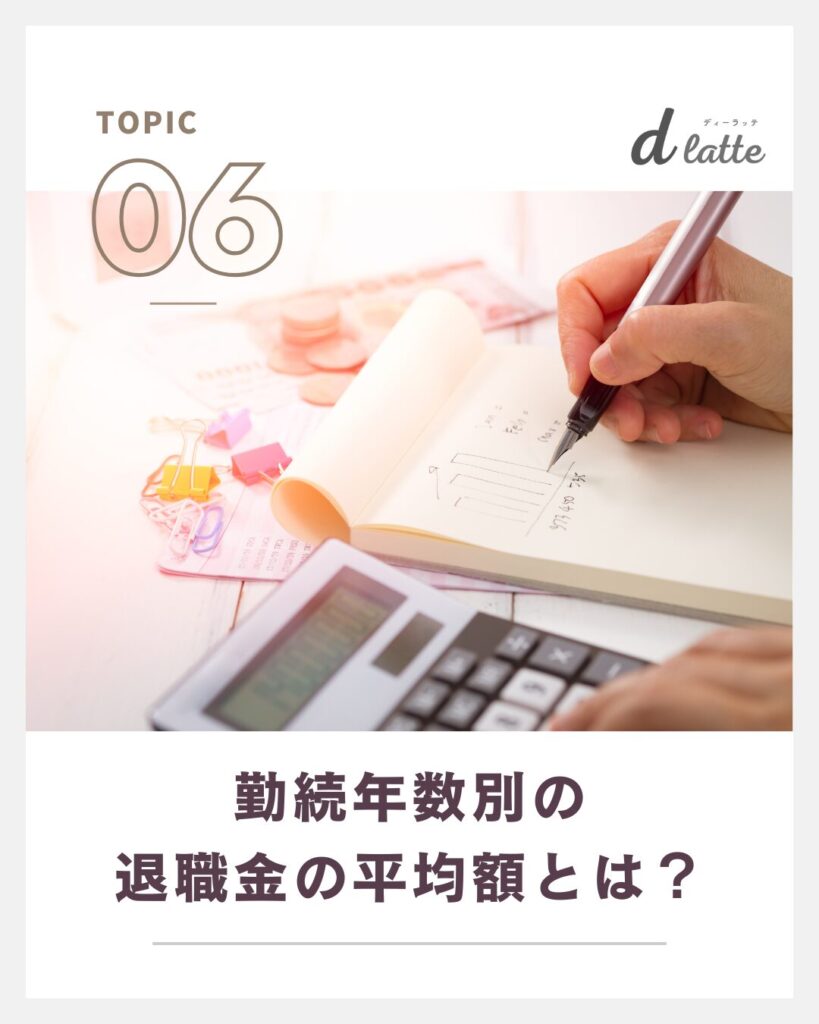
| 月収29万円の場合の退職金の一例 | ||
|---|---|---|
| 勤続年数 | 支給率 | 退職金の目安 |
| 3年 | 0.7 | 20万3千円 |
| 5年 | 1.0 | 29万円 |
| 10年 | 2.4 | 69万6千円 |
| 15年 | 3.0 | 87万円 |
| 20年 | 4.6 | 133万4千円 |
| 25年 | 5.0 | 145万円 |
| 30年 | 7.4 | 214万6千円 |
月収の参考:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」
支給率の参考:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、従業員数10人以上の職場における歯科衛生士の平均月収は約29万円となっています。
上記の表はこの平均月収を基に計算しており、支給率は東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」の医療・福祉系(高専・短大卒/自己都合退職)の支給率を参考にしています。
しかし、実際の支給率や加算・減算方法は勤務先の退職金制度によって大きく異なります。
勤続年数が長いほど退職金の金額も高くなるのが一般的ですが、例えば同じ勤続年数10年でも、Aの歯科医院は退職金が70万円なのに対し、Bの歯科医院は50万円など、大きく差が生じることも珍しくありません。

勤続年数による差が一目瞭然ですが、同じ10年でも医院によって20万円以上の開きがあるなんて驚きですよね。転職を考える時は給与だけでなく、退職金制度の詳細もしっかり確認したいところです。
退職金の支払いや金額の決め方とは?
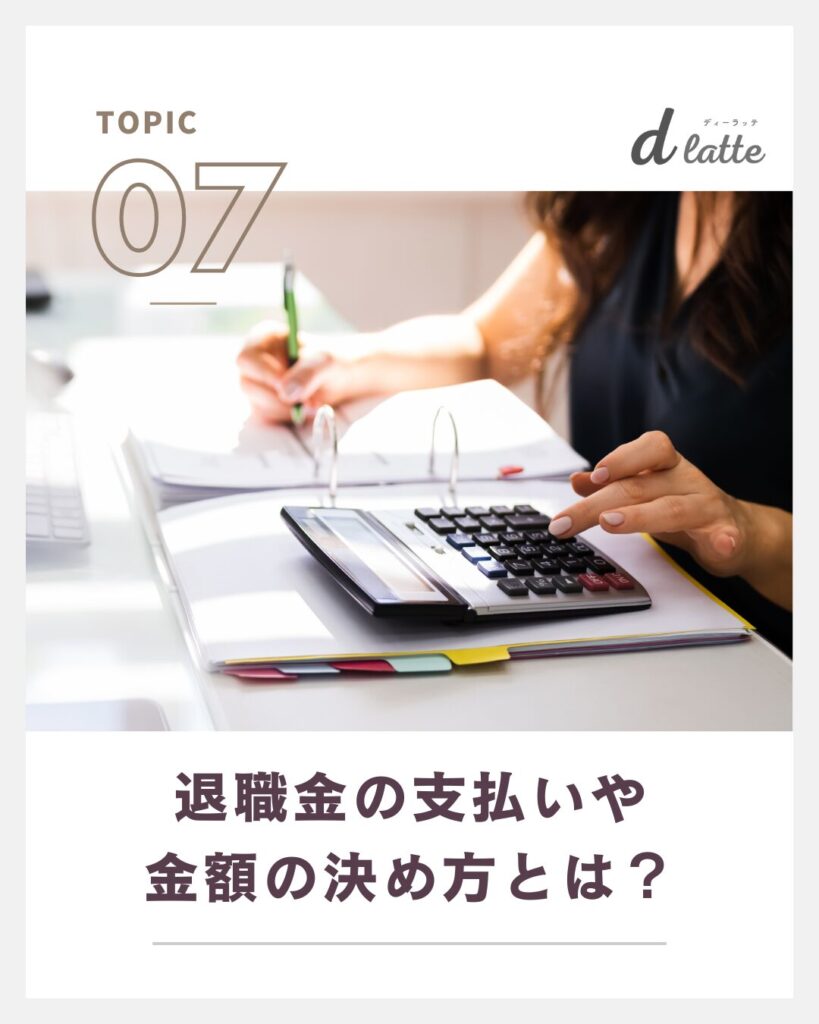
退職金の有無や具体的な金額などは、主に上記のような要素で決まります。どのような制度を導入するかは勤務先によって異なり、計算方法も変わるため、退職金の金額にはかなりの個人差が生じます。ここでは、その主な要素について解説しましょう。
1. 勤務先の方針
退職金の支払いは義務付けられているわけではなく、勤務先の方針によって任意で決められます。そのため、退職金制度を導入しないまま長く経営している歯科医院もあれば、共済などを利用して計画的に準備している歯科医院もあるのです。
退職金制度がある場合は、就業規則を確認すると詳細が分かります。また、求人票にも「退職金制度がある」と記載されているため、就職活動や転職活動中の方は事前に確認しておくとよいでしょう。
2. 退職金制度の種類
- 院長の裁量によるもの
- 中小企業退職金共済
- 生命保険
- 企業年金
歯科医院が導入している退職金制度には、主に上記のような種類があります。共済・生命保険・企業年金は毎月の掛金を積み立てていく方法で、歯科医院側にとっても原資を確保できるといった大きなメリットがあります。
一方、院長の裁量によって退職金が支給される場合は、制度としてきちんと確立されているわけではありません。就業規則に記載されていなければ支払い義務が生じることもなく、従業員の働きぶりや歯科医院の運営状況などによっては支給されない可能性もあります。
3. 退職時の給与額
退職金を計算する上で基本となるのが、退職時の給与額です。一般的に退職金は月収の1~4ヶ月分くらいとされているため、自分の月収で計算すれば大まかな目安がつくと言えます。
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、歯科衛生士の平均月収は約29万円となっています。一方、60~64歳の歯科衛生士の平均月収は約23万円となっており、必ずしも年齢と共に月収が上がり続けるというわけではないようです。
ただ、退職金は月収に支給率をかけて算出するのが一般的で、支給率の割合が金額に大きく影響します。支給率については、次の項目で詳しく説明しましょう。
4. 支給率
支給率とは、退職金の大まかな金額を算出するために月収にかける割合です。具体的な割合は勤務先によって異なりますが、勤続年数が長いほど支給率も高くなるのが一般的です。
仮に定年まで昇給がなかったり、月収が下がってしまった場合でも、勤続年数と共に退職金の支給率が上がれば、ある程度の金額を受け取れることになります。
例えば、歯科衛生士全体の平均月収約29万円と、60~64歳の歯科衛生士の平均月収約23万円を例に計算してみましょう。支給率は仮に勤続年数10年が2.5,30年が7.5とします。
| 勤続年数 | 月収 | 支給率 | 退職金の目安 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 29万円 | 2.5 | 72万5千円 |
| 30年 | 23万円 | 7.5 | 172万5千円 |
上記のように勤続年数に応じて支給率が上がれば、月収が平均より少なくても、退職金に100万円もの差が生じることになるわけです。
5. 役職や貢献度
退職金は単純に月収に支給率をかけるだけでなく、退職時の役職やそれまでの職場への貢献度なども加味されて決まるのが一般的です。
歯科衛生士の場合は、衛生士長・主任・副主任などの役職があります。また、特別な資格の保有者で、その人にしかできない治療を担当していた場合なども、職場への貢献度が高く評価されます。
このようなキャリアの人たちは、退職金にも一定の金額がプラスされることが多いと言えます。
6. 退職の理由
定年前に退職する場合、その理由は「自己都合」か「会社都合」かのどちらかに分かれます。そして、自己都合で退職する人の退職金は、一定の割合で減算されるのが一般的です。
減算方法の規定は勤務先によって異なりますが、支給率の割合も会社都合退職より自己都合退職の方が低くなるケースが大半です。
ちなみに、勤務先を解雇される場合も、退職金の規定が定められていれば、退職金が支給されます。ただし、懲戒処分などによる退職の場合、規定の内容によっては退職金が支払われないこともあります。

退職金の決まり方って、こんなに複雑だったのですね。給与や勤続年数だけでなく、役職や退職理由まで影響するとは。入職時に詳しく聞きにくい内容だからこそ、事前にポイントを整理しておくと安心です。
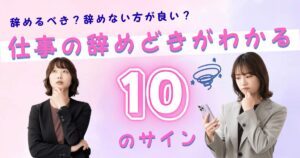
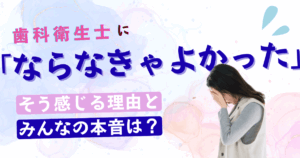
退職金には税金がかかる?
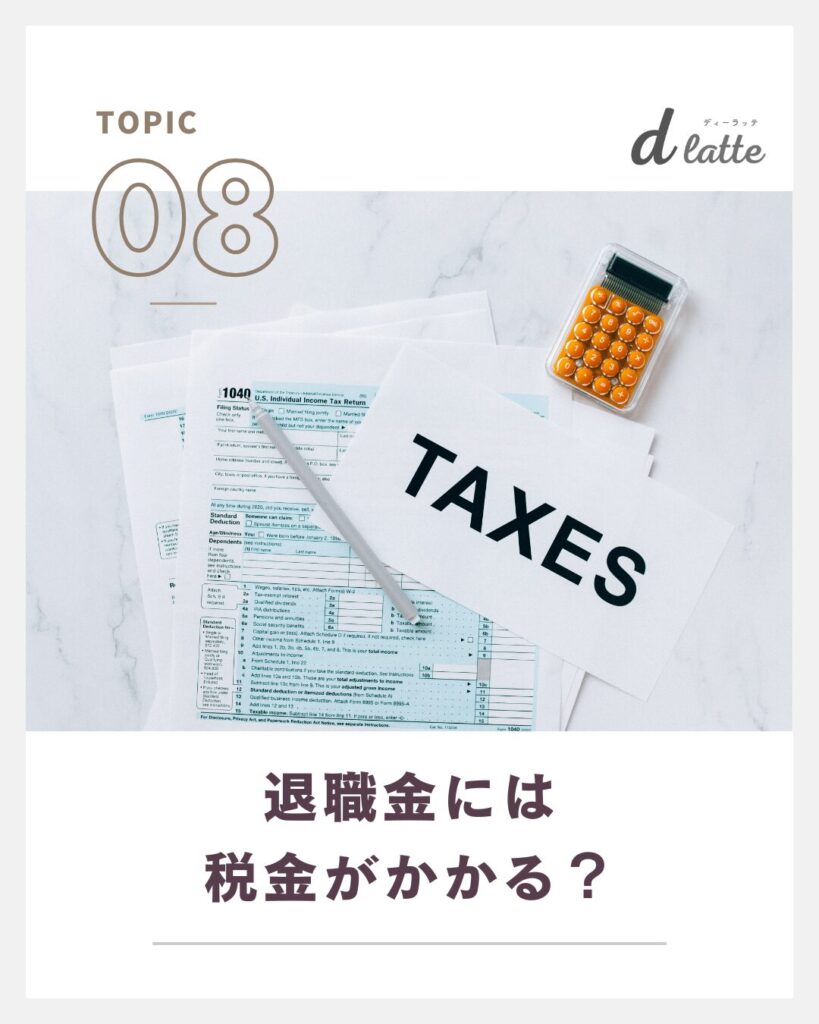
退職金には所得税と住民税がかかります。しかし、通常よりも税負担が軽減されるように「退職所得控除」という優遇措置が適用され、一定の金額までは非課税となります。退職所得控除額は勤続20年以上と20年以下とで以下のように計算方法が異なります。
| 退職所得控除額の計算方法 | |
|---|---|
| 勤続年数20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |
| 勤続20年以上 | 800万円+70万円 ×(勤続年数-20年) |
参考:国税庁「退職金と税」
退職所得控除を受けるには、退職金を受け取る前に勤務先に「退職所得申告書」を提出する必要があります。申告書を提出すると源泉徴収された金額が支給され、確定申告の必要がなくなります。
申告書は勤務先から渡されることが多いですが、指示がない場合は早めに問い合わせしましょう。
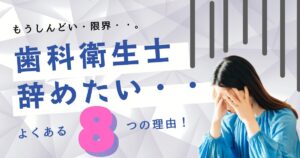
退職金はいつ支給される?
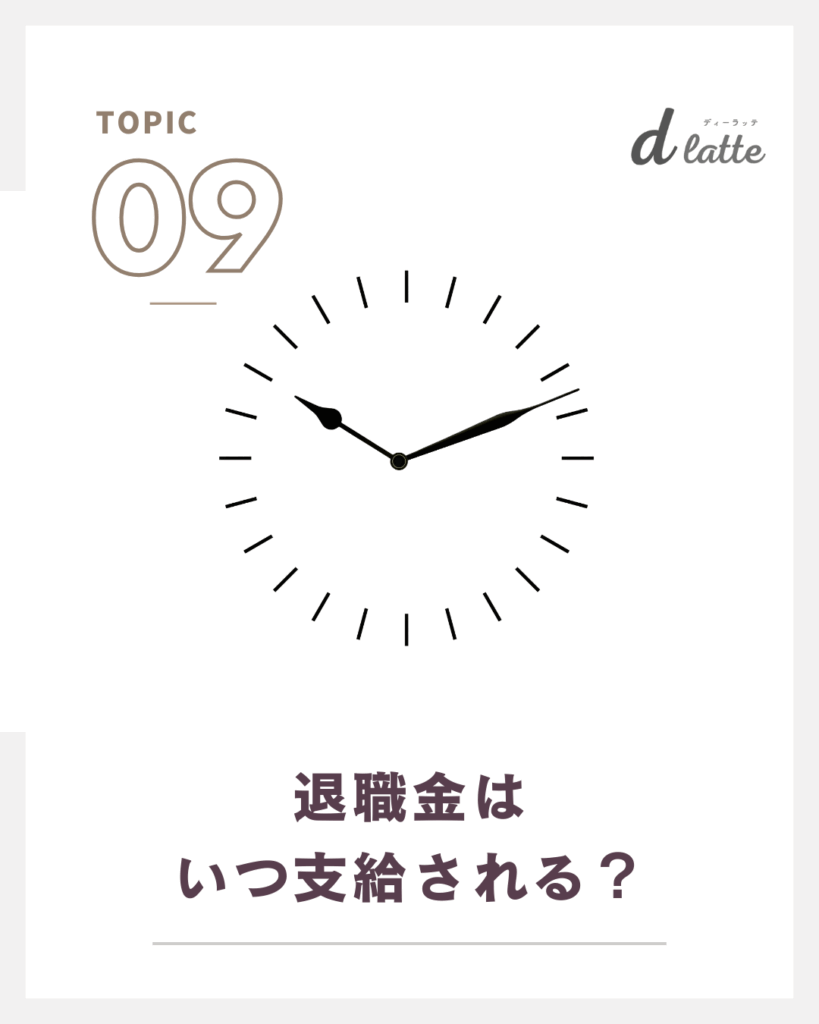
退職後1~2ヶ月後に振り込まれることが多い
退職金の支給方法には、大きく分けて「一時金型」と「年金型」の2種類があります。
一時金型は退職金が一括で支給される方法で、退職してから1~2ヶ月後に振り込まれるのが一般的です。ただし、支払い期限が設けられているわけではないため、手続きに時間がかかるとそれ以上かかる場合もあります。
一方、年金型は退職金を分割して年金として受け取る方法です。どちらの方法で支給されるかは勤務先によって異なるため、就業規則などを確認しておきましょう。

退職金の受取時期って意外と曖昧なものなのですね。退職直後は何かと出費も多いタイミングなので、1~2ヶ月という期間を頭に入れて、資金計画を立てておくことが大切かもしれません。
退職金が支払われない時の対処法

退職金が2ヶ月以上経っても振り込まれない場合は、まず勤務先に確認してみましょう。そもそも退職金が支給される条件を満たしているか、支給予定日はいつ頃かなど、具体的な点を確認することが大切です。
就業規則において退職金の支給が規定されており、退職金を受け取る権利があるにも関わらず、いつまで経っても支給されないという場合は、厚生労働省の労働局や労働基準監督署に相談することがおすすめです。
まとめ
退職金制度を導入している歯科医院は約6割と、決して多いとは言えない割合です。しかし、勤務先の制度が整っていれば、転職などの自己都合退職でも退職金を受け取ることができます。
まずは就業規則をよく確認して、退職金を受け取る権利があるかどうかを確認してみましょう。また、これから就職や転職をする方は、「退職金制度あり」と明記している職場を選ぶと安心ですよ!